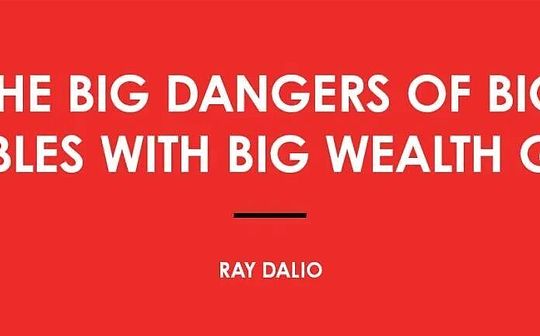著者: Kevin、Movemaker 研究者。出典: X、@MovemakerCN
はじめに:日本のステーブルコインの「二重化」パターン
日本のステーブルコイン市場は「二重軌道」または「二重化」された発展パターンを示しています。このパターンは市場の偶然の進化ではなく、日本独自の規制枠組み、根強い産業ニーズ、そして全く異なる技術導入経路によって形成された「トップレベルの設計」の結果です。
最初のトラックはボトムアップの開発パスです。その代表格がJPYCです。このトラックは法の「柵」内にあり、主にグローバルなパーミッションレスの DeFi エコシステムにサービスを提供します。
2 番目のトラックは、伝統的な金融大手が主導するトップダウンの道です。その中心的な代表は、日本の大手銀行3行(三菱UFJ、三井住友、みずほ)がProgmatプラットフォームに基づいて発行されるステーブルコインの枠組みを共同で推進し、統一するという最近の発表である。このトラックの目標は、規制された機関レベルの企業決済およびセキュリティ トークン (ST) 市場にサービスを提供することです。
この記事では、これら 2 つのトラックを客観的かつ詳細に分解し、最初の柱である法的基盤と技術アーキテクチャの分析に焦点を当てます。企業が運営される法的枠組みは、市場での位置づけをどのように根本的に決定するのか、詳しく見ていきます。従来の金融では解決できなかった、どのような「問題点」を技術的に解決したのでしょうか?特に3大銀行間の制度提携、その裏にある本当の戦略的意図と技術的考察とは何でしょうか?
これら 2 つの軌跡を並べて分析することで、仮想通貨業界における区分管理と並行開発という日本の国家戦略を明らかにします。
1. 複線の解体 – 法的根拠と技術的アーキテクチャ
トラック 1: JPYC の法的進化と「100 万円の壁」
JPYC の市場での位置付けとテクノロジーのユースケースを理解するには、まず 2025 年における JPYC の法的地位の根本的な進化を理解する必要があります。
「前払い商品」から「資金移動商品」へのコンプライアンスのアップグレード
初期の検討段階で、JPYC の運営会社である JPYC Inc. は、柔軟な法的枠組みである「前払式支払手段」を採用しました。この枠組みの下では、JPYC は法的には一種の「ゲーム ポイント」または「ショッピング モールのストアド バリュー カード」に近く、その中心的な特徴は日本円と交換できないことです。
これは当時の規制空白の中では賢明な戦略でした。これにより、複雑な銀行および資金移動法の厳格な規制を回避することに成功し、JPYCが「円建てポイント」として機能することが可能になりました。
しかし、この「灰色」の段階は終わりました。2023年の日本の「金融整理法」の改正により、ステーブルコインは正式に「電子決済手段」として定義され、これに伴いJPYCの法的根拠も強化される必要があります。
JPYCプリペイドモデルは2025年6月に発行終了となります。代わりに株式会社JPYCは長い申請期間を経て「第二種資金移動業」の許可を正式に取得しました。
この「コンプライアンス強化」の意義は大きい。その結果、JPYC の法的地位は根本的に変化しました。換金不可能な「ポイント」から、法的に日本円への換金が許可され、規制に準拠した「資金移動手段」へと変わりました。これにより、法的属性の点で真の「安定通貨」となります。
法的枠組みで定められた市場の上限「100万円の壁」
しかし、今回のコンプライアンス強化は、「償還性」を与えると同時に、「取引限度額100万円」という市場でのポジショニングを決定づける中核的な「足かせ」を課すことにもなった。
日本の「金融整理法」の枠組みによれば、「第二種資金移動業者」免許の主な特徴は、イノベーションを促進しながらマネーロンダリングを厳重に防止し、消費者を保護することにある。この目的のために、1 回の取引には 100 万円の上限が規制されています。
これは、日本の金融業界および仮想通貨業界で一般に「100万円の壁」と呼ばれるコア制限です。
この法的制限は、JPYC の市場での位置付けを根本的に決定します。これは、JPYCは一度の取引で100万円を超える大規模取引には法的に利用できないことを示しています。これにより、大規模な機関間決済、B2B の国境を越えた決済、および (詳細は後述しますが) セキュリティ トークン市場から事実上隔離されます。
したがって、JPYCの技術アーキテクチャとコアユースケースは、「償還性」と「100万円の上限」という2つの前提のもとに開発する必要があります。その技術アーキテクチャは当然ながらパブリック チェーンを指向しています。コアの DeFi 市場にサービスを提供するには、イーサリアム、ポリゴン、ソラナなどのグローバル パブリック ブロックチェーンにデプロイする必要があります。そのスマート コントラクトは、世界中の DEX、融資プロトコル、収益アグリゲーターと自由に組み合わせることができるように、パーミッションレスになるように設計する必要があります。
しかし同時に、このオープン テクノロジ アーキテクチャは、「クラス II」ライセンスの法的上限によって制約されます。これにより、独自のバイナリ状態が作成されます。JPYC は技術的にはグローバルで、権限がなく、上限がありません (スマート コントラクト自体は転送量を制限しません)。しかし、法的には(規制対象の日本の法人または個人に適用される場合)、制限され、上限が定められています。この法律とテクノロジーの「混乱」により、法律とテクノロジーは当然「グレーゾーン」と純粋な Web3 経済に役立つツールになりますが、日本の主流の金融の決済層になることはできません。
トラック 2: 大手 3 行と Progmat の間の「上限のない」制度的提携
さて、トラック 2 に移ります。これはまったく異なる物語であり、Web3 本来の力によってボトムアップで推進されるのではなく、日本の金融の「トップデザイン」によってトップダウンで構築されるものです。
「信託法」に基づく新たな法的根拠
トラック 2 の法的根拠は、JPYC が属する「資金移動業界」の枠組みを完全に回避しています。これは、2023年の「資本破綻処理法」改正における銀行および信託機関向けに調整された「信託ベースのステーブルコイン」の法的道筋に基づいています。
日本の3大銀行(三菱UFJ、三井住友、みずほ)による最近の共同発表は、この新しい法的枠組みに基づいたものです。その中心となる法的構造は次のとおりです。
- <リ>
発行構造:大手銀行3行が「共同信託受託者」となり、三菱UFJ信託銀行が「単独信託受託者」となります。
<リ>
コア機能: これは最も重要な法的な違いです。銀行や信託の免許に基づいて発行される「電子決済手段」には法定取引限度額が100万円ありません。
この法的地位の違いは、日本の規制当局が実施する「トップレベルの設計」を直接反映している。日本は「法治主義」の国であり、市場参加者(特に大手金融機関)の行動論理は「『グレーゾーン』は通過できないことを意味する」である。これは、米国の「司法法学」における「グレーゾーンが一般原則」とは正反対である。
したがって、2023年に新法案が導入されるまで、日本には機関投資家向けのステーブルコイン市場は存在しない。新法案の可決は既存の市場を「規制」するものではなく、機関が参入できる準拠した新しい市場を「創設」するものである。
Progmat プラットフォーム: 「デジタル アセット ナショナル チーム」の技術アーキテクチャを解体する
トラック 2 の参加者は、統合テクノロジー ベースである Progmat プラットフォームを選択しました。その技術的なアーキテクチャを理解するには、まず株主構成を理解する必要があります。
プログマットは2023年に三菱UFJ信託銀行から分社化し独立しました。その株主ラインナップには日本の金融とテクノロジーの中核がほぼ含まれており、「デジタル資産ナショナルチーム」と呼ぶことができます。
- <リ>
信託銀行(発行層):三菱UFJ信託(42%)、みずほ信託(6.5%)、三井住友信託(6.5%)、農中信託(6.5%)。
<リ>
取引所(流通層):JPX(日本取引所グループ、4.3%)。
<リ>
仲介(営業レベル):SBI PTSホールディングス(4.3%)。
<リ>
テクノロジー(インフラレベル):NTTデータ(11.7%)、データチェーン(4.3%)。
したがって、Progmat は破壊的イノベーションを求めるテクノロジー スタートアップではありません。日本の中核金融機関が共同出資する「インフラアライアンス」です。その戦略的目標は、デジタル資産時代(ST、SC、UT)において、日本の統一され、中立的で準拠性のある「国家インフラ」となることです。
Progmat の技術的青写真では、ST (セキュリティ トークン)、UT (ユーティリティ トークン)、SC (安定通貨) が 3 つの中核柱です。STはトークン化される「資産」(不動産など)であり、SCはそれらの資産の支払いと決済に使用される「現金」です。3大銀行によるステーブルコインの発行は、Progmatの壮大な青写真の「ST(RWA)市場」に追加される「支払いと決済のパズル」の最後にして最も重要なピースだ。
銀行ステーブルコインの原動力:「コアバンキングシステム」への技術的な「バイパス」
核心的な疑問が生じます。銀行はすでに成熟した効率的な内部決済システムを備えているのに、なぜ「不必要に」ブロックチェーン上に安定した通貨プラットフォームを構築する必要があるのでしょうか?
その答えは、銀行のステーブルコインは既存のシステムを置き換えることを目的としたものではなく、既存のシステムでは解決できない 3 つの中核的な「問題点」を解決することを目的としているということです。その中で最も重要なのは、銀行自体の IT アーキテクチャの硬直性です。
- <リ>
相互運用性:既存の電子通貨(PayPay、LINE Payなど)は、異なる企業が運営する2つの独立した閉鎖的な「プライベートデータベース」です。それらの間には「相互運用性がなく」、「利用可能な範囲は制限されている」。ブロックチェーンをベースとしたステーブルコイン(SC)は「相互交換」が可能であり、「誰でもどこでもアクセス可能」です。
<リ>
国境を越えた支払い: 従来の「銀行振込」は、「リレーバンク」で構成される長いチェーンを経由する必要があります。このプロセスには「中間コストが高く、到着が大幅に遅れる」。ステーブルコイン システムは、あるアドレスから別のアドレスに直接送られる P2P モデルであり、「最小限の中間コストと即時送金」を可能にします。
<リ>
コアシステムの剛性:これは、銀行が自分の銀行口座(つまり「預金トークン」)を直接開設するのではなく、「なぜ」銀行が「信頼ベースの」ステーブルコインを採用しなければならないかを説明する鍵となります。
– 現状:日本および世界の銀行ITシステムは、「基幹勘定系システム」と呼ばれる、閉鎖的で古いながらも非常に安定したシステムに依存しています。
– 質問:「大きくて、不格好で、古い」システムです。その主な欠陥は、「『書き込み』または『転送』操作をサポートする API がない」ことです。すべての更新 (送金など) は、社内のオンライン バンキング システムを通じて開始する必要があります。
– ジレンマ: 7 時間 24 時間のプログラム可能な外部呼び出しを「銀行会計の中核システム」に直接実装したい場合は、「大規模な変革が必要ですが、これは避けられません」。IT コストと財務安定性のリスクは、どの銀行にとってもほとんど許容できません。
「信頼」構造は、完璧な「バイパス」ソリューションを提供します。
- <リ>
銀行側: 銀行 (委託者として機能) が資金を「信託」(受託者として機能) に転送します。これは標準的で成熟した金融業務であり、毎日行われています。銀行の「基幹業務システム」には新たな開発は必要ありません。
<リ>
信託側: トラスト (Progmat プラットフォームによって強化された) は、ブロックチェーン上で同量のステーブルコインを発行します。
<リ>
鎖の上に:今後は、24時間365日のプログラム可能なスマートコントラクト通話とB2B自動決済はすべて、銀行の「中核的な銀行会計システム」から完全に分離された信頼レベルとブロックチェーンレベルで行われます。
<リ>
償還する: ユーザーが償還する必要がある場合、信託はチェーン上の安定した通貨を破棄し、従来のパスを通じて法定通貨を銀行口座に返します。
このアーキテクチャは、銀行の中核となる会計システムにまったく触れることなく、24時間365日、低コストで国境を越えて銀行預金を提供し、そして最も重要な「プログラマビリティ」を提供します。
2. 「DeFi」と「機関」の市場での位置付け
JPYC は「第二種資金移動業」の許可と「取引限度額 100 万円」によって定義されていることがわかります。一方、Track 2 (Progmat Alliance) は、「信託型」ライセンスに基づいて「取引制限なし」の機関レベルの決済ネットワークを構築します。
これらは、市場の定義、顧客のセグメント化、特定の問題点の解決の鍵となります。この章では、これら 2 つのトラックによってどのコア ユーザーの緊急ニーズが満たされるのか、また、従来の金融と Web3 経済における特定の「問題点」が解決されるのかについて、詳細な分析を行います。
JPYC: グローバル DeFi を提供する「オンチェーン日本円」
JPYC のコア ユーザー グループ: 取引額が 100 万円未満のグローバルでパーミッションレスな暗号ネイティブの経済参加者。
JPYC が解決する中心的な問題点は、グローバル DeFi エコシステムに重要な資産である「オンチェーン日本円」が欠如していることです。
問題点 1: DEX の流動性と 24 時間 365 日の日本円外国為替市場
グローバルな分散型取引所 (DEX) では、USDC、USDT、ETH、および WBTC が流動性の基礎を形成します。しかし、世界の主要な準備通貨および取引通貨の一つである日本円は長い間存在しませんでした。
JPYC の登場は、準拠した償還可能な初のオンチェーン日本円ソリューションです。その中心的な使用例の 1 つは、JPYC/USDC または JPYC/ETH 取引ペアの流動性ベースとしてです。これにより、本質的に効率的な日本円のスポット外国為替市場が形成され、世界中のDeFiユーザーがいつでも日本円を主流の暗号資産と交換できるようになります。その中心的なユーザーは、世界的な DeFi トレーダー、裁定取引者、および日本円のエクスポージャーを必要とする Web3 プロトコルです。
問題点 2: 日本のマクロ経済環境を「トークン化」する裁定取引ツール
金融レベルにおけるJPYCの最も核心的かつユニークなユースケースは、日本独特のマクロ金融環境である長期低金利政策をうまく「トークン化」し、それをDeFiに導入することにある。
従来の金融分野では、これが世界的に有名な「円キャリートレード」を生み出しました。機関投資家が極めて低コスト(ほぼゼロ)の日本円を借り入れ、高利回りのドルに交換し、高金利資産(米国債など)に投資することで、日本円の巨大な金利差を着実に獲得するというものです。
しかし、この業務は伝統的に機関の管轄であったため、一般の投資家が参加するのは困難でした。JPYC が解決する問題点は、このプロレベルの財務戦略を「分散化」し、「許可を必要としない」ことです。
「100万円制限」という法的枠組みの下では、JPYCはたまたまDeFiプレーヤーにとってそのような裁定取引を行うための完璧なツールとなっている。典型的な「オンチェーン日本円裁定取引」の経路は次のとおりです。
- <リ>
住宅ローン:DeFiユーザーは、保有するETHまたはWBTCを担保としてAaveやCompoundなどの分散型融資プロトコルに預けます。
<リ>
貸す:ユーザーはJPYCを貸与することを選択します。法定通貨に固定されたゼロ金利環境のため、チェーン上のJPYCの借入金利(Borrow APY)は非常に低く、他の主流資産よりもはるかに低いです。
<リ>
交換:ユーザーは借りたJPYCをDEX(CurveやUniswapなど)ですぐに売却し、高金利のUSDステーブルコイン(USDCやUSDTなど)と交換します。
<リ>
利息を得るために預金する:その後、ユーザーは交換したUSDCを貸付契約の預金プールまたは収入アグリゲーター(Yarn Financeなど)に預け入れて、JPYCの借入コストよりも大幅に高い預金金利(APYの供給)を取得し、それによって両者の金利差を取得します。
この「JPYCを貸し出してUSDCに交換する」という行為自体が、チェーン上で実行され日本円で価格設定される空売り行為です。JPYC の償還可能性、パブリック チェーンの構成可能性、および 100 万円という上限は、このような低額から中額の高頻度の裁定取引を実行する世界的な DeFi トレーダーのニーズと一致しています。
問題点 3: Web3 エコシステム内での日本円のマイクロペイメント
さらに、JPYC は日本のローカル Web3 エコシステムにもサービスを提供しています。NFT マーケットプレイス、オンチェーン ゲーム、Web3 アプリケーションの開発者にとって、少額決済用のネイティブの日本円支払いツールが必要です。JPYC はまさにこの「少額決済」と「エコロジー決済」のニーズに応えます。
Progmat:TradFiを提供する「B2B機関決済ツール」
JPYC とは対照的に、トラック 2 の Progmat Alliance の中心的なユーザーは、グローバルな DeFi トレーダーではなく、日本および世界中の大企業、機関投資家、証券会社、銀行です。
解決したいのは、JPYCが触れられない、日本の主流の金融システムにおけるシステム上の「問題点」だ。
課題 1 (社外): B2B 国境を越えた企業資金決済 (SWIFT 課題)
従来の B2B の国境を越えた支払いの問題点は世界中にあります。SWIFT システムを介した銀行送金は、「リレー バンク」の複雑なチェーンを通過する必要があります。このプロセスでは、高い中間コスト(手数料、為替差額)が発生するだけでなく、さらに深刻なのは、適時性が極めて低いこと(T+N 到着)と 7×2 時間以外の運用制限です。
三菱商事のような世界的な総合商社にとって、日々世界中で膨大な決済ニーズがあります。Progmat プラットフォームに基づくステーブルコインは、3 つの大手銀行に代わる初の準拠した上限のない P2P 代替手段を提供します。これにより、企業はあるアドレスから別のアドレスに直接即時送金を行うことができ、中間コストを最小限に抑えることができます。その中心的なユーザーは多国籍企業の財務部門です。
課題 2 (内部): 銀行コア システムの最新化
「信頼ベースの」ステーブルコインによって解決される 2 番目のコア ユーザーの問題点は、銀行自体の問題点です。
「バイパス」アーキテクチャ (銀行 ➡️信託 ➡️ ブロックチェーン) の巧妙な点は、銀行の中核となる会計システムにはまったく触れずに、銀行の預金 (円) に「プログラム可能性」を与えていることです。これは、低コスト、低リスク、高効率の銀行システム最新化ソリューションです。
課題 3: セキュリティ トークン市場における「デポジットと支払い」(DVP の課題)
B2B 決済がその直接の応用である場合、Progmat ステーブルコインの最終的な目標は、そのエコシステムのもう 1 つの柱であるセキュリティ トークンに「キャッシュ バックボーン」を提供することです。
金融市場の決済の基礎となるのは、「Deposit vs Payment」の略であるDVP(Deliver versus Payment)です。
- <リ>
伝統的な集落:T+2決済サイクルでは、買い手と売り手の間に大きな「信用リスク」と「時間差」が生じます。
<リ>
オンチェーン DVP: 買い手は「お金」(つまり、Progmat ステーブルコイン)を保持し、売り手は「資産」(つまり、Progmat セキュリティトークン)を保持します。スマートコントラクトを通じて、両者は「同時交換」(アトミック交換)を実現できます。
これはすでに存在する巨大な市場に基づいています。プログマットのデータによると、2025年秋時点で日本国内のSTケースの累計発行額は2,800億円以上に達し、STケースの市場残存価値総額は5,600億円(約38億米ドル)以上に達している。
発行されたSTのうち、金額ベースで86%以上が不動STでした。
この急速に成長するセキュリティトークンとRWA市場は、数千億円の価値があり、現在、コンプライアンスに準拠した効率的でネイティブな「オンチェーン現金決済ツール」が不足しています。
したがって、3 つの大手銀行が共同発行する「上限なし」ステーブルコインの中心的な戦略的ユーザーは、この数千億の ST/RWA 市場です。その目標は、この新興資本市場において唯一準拠した機関グレードの DVP 決済ツールとなり、それによって Progmat プラットフォーム上で「資産発行」と「資金決済」の最終的な閉ループを完成させることです。
3. 大手3行の戦略の真意
「問題点」の解決は表面的な「戦術目標」にすぎません。本当に答える必要がある深い質問は次のとおりです。
- <リ>
なぜ「同盟」なのか?伝統的な金融分野で最大の競争相手である三菱UFJ、三井住友、みずほの3社は、なぜこの基幹路線で「共同」することを選んだのか。
<リ>
なぜ「プログマット」なのか?なぜ各銀行はそれぞれ独自のプライベートプラットフォームを構築せず、三菱UFJ信託銀行から「分社化」され株式を分散した「中立的」な組織に将来の金融の中核インフラを委ねることを選択するのだろうか。
これら 2 つの質問への答えによって、日本のトップレベルの財政設計の背後にある本当の最終的な戦略的意図が明らかになる可能性があります。
意図 1: 「中立的なプラットフォーム」 – 業界の「最大公約数」を構築する唯一の方法
日本の 3 つの主要銀行の提携は、Progmat ステーブルコインの枠組み全体の中で最も思慮深い戦略的決定です。従来の金融の世界では、支払いと決済は銀行の中核で最も競争力のある分野です。どの銀行(三菱 UFJ など)でも、プライベートで独占的なステーブルコイン決済プラットフォームを構築し、競合他社(みずほや三井住友など)に参加と使用を要求することは商業的に不可能です。
主要な競合他社が管理するインフラ上で将来の中核となる決済ビジネスを運営しようとする金融大手は存在しない。
したがって、業界全体が採用できる全国レベルの「機関決済ネットワーク」を構築するには、「中立性」が前提でなければならないことは、大手3行とも認識している。
これが、Progmat プラットフォームが歴史的な舞台に登場した中心的な理由です。プログマットの株式保有構造の設計は、この「中立性」の戦略的考慮を完璧に示しています。同社は2023年に三菱UFJ信託銀行から独立した。三菱UFJ信託銀行は依然として筆頭株主(42%)であるが、その支配力は意図的に希薄化されている。
さらに重要なのは、みずほ信託、三井住友信託、SMBC、さらには農中信託がすべて中核株主として6.5%の株式保有率で結ばれているということだ。同時に、「流通」を代表するJPX(日本取引所グループ)、「販売」を代表するSBI、「技術」を代表するNTTデータも提携に加わった。
この「オールスター」株式構成の目的は、市場に明確なシグナルを送ることである。つまり、プログマットは三菱UFJの「私有財産」ではなく、日本の金融の中核勢力が共同で資金提供し、認めている「業界の公共インフラ」であるということである。
三菱 UFJ は、単一組織の絶対的なコントロールを犠牲にすることで、コントロールよりもはるかに価値のあるもの、つまり業界全体での採用とコンセンサスを獲得しました。これは統一された「代表チーム」のインフラを構築するために支払わなければならない「代償」であり、それが成功への唯一の道でもある。
意図 2: 防御と反撃 — 「TradFi コンプライアンスの堀」の構築
3大銀行の共同行動は「新大陸建設」に向けた攻撃であるだけでなく、重要な「守りの反撃」でもある。その防御の対象は、グローバルなパーミッションレス暗号通貨 (USDC、USDT など) と、JPYC のような新規プレーヤーです。
伝統的な金融大手の観点から見ると、もしこれらの「非ソブリン」および「ノンバンク」のステーブルコインがB2B決済や証券決済の分野に浸透することを許されれば、その結果は悲惨なものとなるだろう:銀行の中核的決済ビジネスは完全に「中抜き」されるだろう。
したがって、Web3の力が圧倒的になる前に、大手3行が主導権を握る必要がある。その戦略ロジックは古典的な「受け入れ、拡張し、組み込む」です。
- <リ>
抱擁: ブロックチェーン技術を積極的に採用し、DVP や国境を越えた支払いにおけるブロックチェーン技術の優位性を認識します。
<リ>
拡大する:その最も強力な武器である規制上の信託と法的リソースを利用して、2023年の「金融破綻処理法」改正を推進し、銀行と信託機関限定の「無制限」「信託型」ステーブルコイン法的枠組みを創設します。
<リ>
組み込む:この「トップレベル設計」により、市場の「二分化」に成功しました。
-円:「100万円の壁」という法的枠組みによって、DeFiと小売マイクロペイメントの「サンドボックス」に恒久的に「封じ込め」られ、機関レベルの体系的な金融サービスに関与できなくなっている。
-プログラムマット: 3 つの主要銀行および取引所によって承認された、準拠した無制限の唯一の「機関チャネル」になります。
この戦略を通じて、日本の金融大手は、Web3 イノベーションを阻害することなく、深い「TradFi コンプライアンスの堀」を構築することに成功しました。彼らは法的枠組みを利用して、近い将来、すべての高額で体系的な金融活動は、彼らの管理下にある「トラック 2」でのみ運営されなければならず、また実行できないことを保証します。
意図 3: 「RWA エコノミー」の「決済および料金所」を独占する
「中立性」が組織形態であり、「コンプライアンスの堀」が防御手段であるとすれば、その最終的かつ中核となる戦略的意図は「攻撃」、つまり日本の次世代デジタル金融を完全にコントロールする「中核料金所」である。
セキュリティ トークンの新興の「資産側」では、Progmat プラットフォームが発行シェアの 64.6% を占め、ほぼ独占的な先行者利益を達成しています。
大手銀行 3 行の提携による戦略的な閉ループが完全に明らかになりました。
- <リ>
最初のステップ(資産側):Progmatプラットフォームを通じて、日本のST/RWA(不動産、債券)の「資産発行」をいち早く独占する。
<リ>
ステップ2(現金側): 3 つの主要銀行の提携を通じて、統一された上限のない Progmat Stablecoin (SC) が発行され、この数千億の ST 市場で唯一準拠した「現金決済」ツールとなります。
結論:日本の「ゾーン・アンド・ビルド」デジタル資産戦略
上記の分析を通じて、「複線システム」パターンと日本の安定通貨の将来について客観的な結論を導き出すことができます。現在の市場段階では、JPYC と Joint Stable は直接的な競争関係にありませんが、まったく異なる市場にサービスを提供する並行軌道にあります。それらは非常に異なるユーザー グループにサービスを提供し、非常に異なる市場の問題を解決します。
日本円ステーブルコインは「ゾーニング監督」と「トップレベル構築」の段階に入った。一方で、規制当局は、JPYC のようなボトムアップの Web3 小売イノベーションを監督下に持ち込みました。同時に、彼らのために「規制のサンドボックス」を設置した。これは、これらのイノベーションがもたらす可能性のあるシステミックな金融リスクを地域の中核金融システムから「隔離」するために法的なファイアウォールを確立するようなものです。一方、規制当局は、日本の金融システムの中核である企業決済と資本市場を直接指摘し、銀行と信託機関向けの新たなコンプライアンス経路を「トップレベルで設計」した。
今後 3 年間を見据えると、これら 2 つのトラックが並行して発展し続ける可能性が高くなります。Track One は、DeFi、Web3 ゲーム、小売決済におけるイノベーションを引き続き模索していきます。トラック 2 では、日本の数兆ドル相当の RWA の「証券トークン化」(ST) と、銀行ステーブルコイン (SC) を通じたその効率的な流通に焦点を当てます。