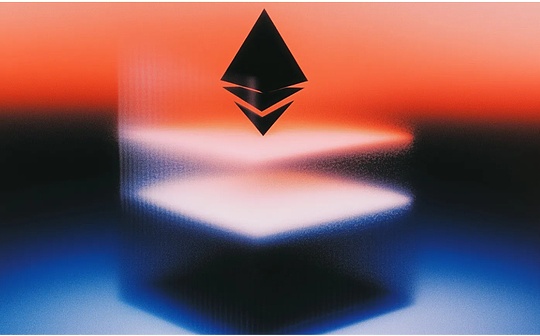<スパンリーフ="">著者: 張峰
<スパンリーフ="">世界の暗号化市場が「野蛮な成長」から「コンプライアンスと主流化」へと変化する中、機関投資家からの大量の資金流入により、市場の価格設定メカニズムが再形成されています。アメリカのソフトウェア会社Strategyによるビットコインの大規模購入から、香港のBoyaa InteractiveによるWeb3分野への暗号化資産の割り当てへの転換まで、ますます多くの上場企業がデジタル通貨をバランスシートに組み込んでいる。
<スパンリーフ="">しばらくの間、この種の「コインと株式のリンケージ」、つまり仮想通貨と株式市場の間の連動操作は、もはや個々の企業による単なる危険な試みではなく、従来の上場企業と仮想通貨の世界との間の重要な架け橋になりつつあります。しかし、通貨と株式の連動は企業評価の論理をどのように変えるのでしょうか?おそらく、それは暗号通貨を購入するほど単純ではなく、評価ロジックの体系的な再構築である可能性があります。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">1. 内部基盤: デジタル化の 3 つの側面
<スパンリーフ="">企業の暗号通貨ビジネスへの関与が従来の評価ロジックを変えることができる本質的な基盤は、デジタル手段を通じて、透明性、エコロジカルなオープン性、トランザクション・インテリジェンスという 3 つの側面から企業価値の基盤を再構築することにあります。
<スパンリーフ="">透明性の向上<スパンリーフ="">これは、ブロックチェーン技術と上場企業の情報開示要件が自然に適合した必然の結果です。分散型台帳技術としてのブロックチェーンの中核的な特徴は、改ざんが不可能であり、プロセス全体が追跡可能であることです。ブロックチェーンを基盤とした情報開示システムは、財務データや業務データのリアルタイムかつ改ざん不可能な記録を実現し、規制当局の検証コストを大幅に削減します。上場企業が売掛債権の一部をRWAという形でトークン化し、ブロックチェーン上で流通させると、これらの資産の真正性、流通記録、所有権の変更が永続的に記録され、改ざんや隠蔽を技術レベルで行うことが極めて困難になります。
<スパンリーフ="">コミュニティへの参加が拡大<スパンリーフ="">実際、それは新しいタイプの生態学的価値とネットワーク効果を構築します。 Web3 の中核的な機能の 1 つは、コミュニティ主導の分散型ガバナンスです。上場企業は暗号通貨ビジネスを通じてコミュニティへの参加を拡大し、従来の評価モデルにおける成長の前提と限界収益の期待を直接変えます。商品またはサービスのトークンは、ユーザーを企業サービスの詳細な利用に引きつけます。支払いトークンは、エコシステム内の経済循環とユーザーの粘着性を促進します。株式トークンはユーザーを株主に変え、利益の調整とガバナンスの共有を実現します。
<スパンリーフ="">インテリジェントな機能強化<スパンリーフ="">スマート コントラクトや分散型自律組織などの Web3 技術革新を通じて、上場企業は暗号化ビジネスの高度な自動化を実現し、すべての関係者の参加コストを大幅に削減し、業務効率を向上させることができます。スマート コントラクトに基づく自動実行により、中間リンクと手動介入を大幅に削減できます。仮想通貨マイニングに携わる上場企業は、スマートコントラクトを通じて、電気料金の支払い、マイニングマシンのメンテナンスとスケジュール設定、マイニング収益の分配などのプロセスを自動的に完了できるため、運営コストが削減されるだけでなく、プロセスの信頼性と透明性も向上します。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">2. 基本モデル:暗号化ビジネスへの3つの参加方法
<スパンリーフ="">暗号化技術の核となる特性に基づいて、企業の暗号化ビジネスへの参加は主に次の 3 つの革新モデルを導き出し、従来のビジネス ロジックを異なる次元から再構築します。
<スパンリーフ="">ブロックチェーンに基づく透明な運用モデル。<スパンリーフ="">主要な資産 (売掛金やサプライ チェーンの請求書など) をトークン化し、チェーン上に置くことで、企業は運用データの改ざんのない完全な追跡可能性を実現できます。このモデルは、従来の閉鎖的な財務監査を、24時間市場の監督を受ける「ガラスの箱」業務に変換し、投資家の信頼を高め、コンプライアンスと監査のコストを大幅に削減します。
<スパンリーフ="">トークンエコノミーのオープンなエコロジカルモデルを構築します。<スパンリーフ="">企業は、特定の権利と利益を持つエコロジートークン(ポイント、NFT、またはガバナンストークン)を発行することで、自社のビジネスエコシステムをユーザーやサードパーティ開発者に積極的に公開します。これにより、ユーザーの貢献が定量化され、それらが取引可能な資産に変換されるだけでなく、互換性のあるトークン経済モデルを奨励することでエコシステムを共同で構築する外部リソースも呼び込み、強力なネットワーク効果とユーザーの粘着性を形成します。
<スパンリーフ="">スマートコントラクトに依存した自動取引モデル。<スパンリーフ="">企業は AI とスマート コントラクトを組み合わせて使用し、複雑なビジネス ロジック (著作権配当、サプライ チェーン決済、貿易金融など) を自動的に実行されるデジタル契約にエンコードします。このモデルは、「コード イズ ロー」ビジネス プロセスの自動化を実現し、従来の取引における仲介者への依存を軽減し、取引効率を向上させ、運用リスクと摩擦コストを削減します。
<スパンリーフ="">実際には、戦略上のニーズに応じて、上記の 3 つのモードを 2 つまたは 3 つに統合することもできます。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">3. 評価の基準ロジックを変更します。伝統的で静的なものから、技術的で動的なものに変更します。
<スパンリーフ="">通貨と株式の連動により、上場企業の評価基準ロジックが、静的な資産評価から動的な評価へ、また伝統的な産業からテクノロジーやスマート産業へと変化する可能性があります。
<スパンリーフ="">従来の評価モデルでは、有形資産とキャッシュ フローが中心的な参照フレームです。通貨と株式の連動により、仮想通貨の世界に価値測定基準が導入されます。上場企業がさまざまなトークンを発行してエコシステムを構築すると、その価値の成長はメトカーフの法則に従います。ネットワークの価値は、従来の線形成長の仮定ではなく、ユーザー数の 2 乗に比例します。
<スパンリーフ="">テスラの事例は、この評価基準ロジックの変化を完璧に示しています。イーロン・マスクのリーダーシップの下、テスラは通貨と株式の連動を世界的に認められた財務パフォーマンスアートと戦略的実践に変えました。同社はビットコインを購入して支払いを受け入れるだけでなく、マスク氏はソーシャルメディアを通じて仮想通貨の価格に直接影響を与え、それがテスラの株価に影響を与えることになる。
<スパンリーフ="">テスラのビットコイン購入は、市場ではテスラが自動車会社であるだけでなく、将来を見据えたテクノロジー投資会社でもあると解釈されている。<スパンリーフ="">この物語は、投資家の同社に対する評価の枠組みを変え、従来の自動車メーカーの評価ロジックからテクノロジーエコシステムの評価ロジックに移行しました。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">4. 価値形成のロジックを変える:サイクル確認からリアルタイム発見へ
<スパンリーフ="">コインストックのリンクは、定期的な確認からリアルタイムの価格発見へと移行し、価値形成のロジックを変える可能性もあります。のように<スパンリーフ="">エコロジートークンを発行することにより、企業はコンテンツ作成、コミュニティプロモーション、データ貢献などのあらゆるユーザーインタラクションを特定のトークン報酬として定量化します。このメカニズムは、ユーザーを受動的な消費者から積極的な参加者およびエコロジーの共同構築者に根本的に変えます。ユーザーが貢献に対して取得したトークンを保持すると、ユーザーの利益はエコシステムの繁栄に深く結びつき、ユーザーの粘着性が大幅に高まります。さらに重要なことは、組み込みの経済的インセンティブツールとしてのトークンは、ユーザーの参加と創造性を継続的に刺激し、それによって巨大な集合知を集めてエコロジーの革新と開発を共同で促進することができるということです。
<スパンリーフ="">これにより、従来の価値形成ロジックが完全に変わります。<スパンリーフ="">企業の価値は、四半期ごとの財務報告によって定期的に確認されるだけでなく、刻一刻とユーザーの参加と貢献を通じて継続的に形成され、発見され続けています。<スパンリーフ="">このように、トークンの価値と流通状況は、企業の生態系の活力と将来の成長可能性を測定するためのリアルタイムの「ダッシュボード」となっています。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">5. 価値成長のロジックを変更する: 直線的な成長から生態学的相乗効果へ
<スパンリーフ="">通貨と株式の連動は、上場企業の価値成長ロジックを、社内の比較的閉鎖的な直線的成長から、比較的オープンな協調的成長へと変化させる可能性もあります。
<スパンリーフ="">従来の評価モデル<スパンリーフ="">これは多くの場合、過去の財務データと線形成長の仮定に基づいていますが、活発なコミュニティを持つ Web3 企業の価値の成長はメトカーフの法則に従います。つまり、ネットワークの価値はユーザー数の 2 乗に比例します。上場企業が暗号通貨ビジネスや複数種類のトークンの発行を通じて強固なコミュニティエコシステムを構築すると、顧客獲得コストが大幅に削減され、ユーザーの定着率が向上し、生涯価値が向上します。これらの要素は評価倍率に反映される必要があります。
<スパンリーフ="">香港に上場しているテクノロジー企業の事例は、この価値成長ロジックの変化を示しています。同社は親会社として仮想通貨を直接購入することはありませんが、自社または関連子会社や投資ファンドを通じて複数の主流の仮想通貨およびブロックチェーンプロジェクトに大規模に投資しています。投資の方向性は中核事業(クラウドサービス、ゲーム、ソーシャルなど)と密接に関連しており、将来のエコシステムの構築を目指しています。この種の「仮想と現実の組み合わせ」による生態学的相乗効果のストーリーは、単純な通貨投機よりも説得力があり、持続可能です。<スパンリーフ="">それは、内部資源の蓄積への依存から、環境に優しい価値の共有へと、価値成長の基本的なロジックが変わるからです。
<スパンリーフ="">ナスダックはSECにルール変更申請を提出し、同社市場でのトークン化された証券の取引を促進する計画を立てており、これは伝統的な金融大手が資産のトークン化の変化を積極的に受け入れていることを示している。仮想通貨の規制が徐々に明確になり、基盤となるテクノロジーがますます成熟し、機関の採用率が増加し続けるにつれて、通貨と株式の連動モデルはより多様化および標準化され、進化し続けることが予想されます。
<スパンリーフ="">もちろん、投資家がビットコインを直接購入できるようになると、ビットコインを保有する企業に追加のプレミアムを支払う意欲がなくなる可能性があることを考慮する必要があります。つまり、市場効率が向上すると、<スパンリーフ="">通貨と株式の連動による価値形成ロジックは今後も進化していくだろう。将来、通貨と株式の連動性は、意図的に強調する必要がある概念ではなくなり、新しい経済生態学の自然かつ自然な基礎法則となるでしょう。